
 女性蔵元 吉田 由香里氏/女性杜氏 吉田 真子氏
女性蔵元 吉田 由香里氏/女性杜氏 吉田 真子氏
福井県吉田郡永平寺町にある吉田酒造。蔵元の吉田由香里氏と杜氏の吉田真子氏が中心となり、
酒造りを行っています。地に根差し、風土を生かし、この郷ならではの美酒を醸すことを追及する
「永平寺テロワール」を大切にしています。






酒造りを行っています。地に根差し、風土を生かし、この郷ならではの美酒を醸すことを追及する
「永平寺テロワール」を大切にしています。


山から吹く風、川を渡る風を受け、あぜ道に立つと、その土地が生み出した人間そのものの色合いと息づかいが聞こえてきそうです。そして、そこで感じるのは、目の前に広がる大自然への畏敬の念と感謝。そして、これら土地に根差し、風土を生かした酒造りの源が永平寺テロワールです。
今年(令和2年)は吉田酒造、苗を育てるところから挑戦しています!

210年以上も昔の文化三年(1806年)から永平寺の地に酒蔵を構え、霊峰白山の雪解けの伏流水とその水で育まれた米で米作りを続けています。
5代目、吉田忠智氏が酒蔵を継いだ時、白龍は福井県内で一番製造石数が少ない小さな小さな酒蔵でした。東京農業大学、国税局・醸造試験場で酒造りを学んだ6代目蔵元・吉田智彦氏は、質の高いお酒でお客様に喜んでいただこう!と考え、その原材料となる米「山田錦」を購入しようとしたが、「前年度実績がないので米を売れないと」断られ、どうしたら良かわからずに混沌とした日々を過ごしていました。 その様な折、精米をお願いしているパールライス工場のベテラン精米杜氏の横井氏から「吉田さんのとこ田舎で田圃がぎょうさん(たくさん)あるんやで、自分で山田錦を作ったらどうやの。」との衝撃的な一言をいただき、一筋の光が見えた瞬間でした。 「安心してお酒を飲んでもらうために、恵まれた上志比村の大自然の中で、化学肥料は使わない。農薬も、できるだけ使わないで、米にこだわり酒米最高峰の山田錦を自ら作り、その米で米の命が生きている旨い酒を造る。」と、決心したのは平成元年でした。
当時、山田錦栽培の北限はぎりぎり福井県となっており、県内で山田錦の栽培に着手はしても反あたりの俵数がとれず、どこも山田錦の栽培が続く事はありませんでした。山田錦は、晩生で背丈が高く台風に弱い。米粒が大きく、米粒中央に大きな心白があることが山田錦の特徴だが、コシヒカリの様に収量があると、米粒が小さくなり高精白する酒造りには向かない。今まで、化学肥料を米作りに使用していたので、土壌改良に3年かかると言われました。
米の命が生きている。
酒は、生きている。
5代目、吉田忠智氏が酒蔵を継いだ時、白龍は福井県内で一番製造石数が少ない小さな小さな酒蔵でした。東京農業大学、国税局・醸造試験場で酒造りを学んだ6代目蔵元・吉田智彦氏は、質の高いお酒でお客様に喜んでいただこう!と考え、その原材料となる米「山田錦」を購入しようとしたが、「前年度実績がないので米を売れないと」断られ、どうしたら良かわからずに混沌とした日々を過ごしていました。 その様な折、精米をお願いしているパールライス工場のベテラン精米杜氏の横井氏から「吉田さんのとこ田舎で田圃がぎょうさん(たくさん)あるんやで、自分で山田錦を作ったらどうやの。」との衝撃的な一言をいただき、一筋の光が見えた瞬間でした。 「安心してお酒を飲んでもらうために、恵まれた上志比村の大自然の中で、化学肥料は使わない。農薬も、できるだけ使わないで、米にこだわり酒米最高峰の山田錦を自ら作り、その米で米の命が生きている旨い酒を造る。」と、決心したのは平成元年でした。
当時、山田錦栽培の北限はぎりぎり福井県となっており、県内で山田錦の栽培に着手はしても反あたりの俵数がとれず、どこも山田錦の栽培が続く事はありませんでした。山田錦は、晩生で背丈が高く台風に弱い。米粒が大きく、米粒中央に大きな心白があることが山田錦の特徴だが、コシヒカリの様に収量があると、米粒が小さくなり高精白する酒造りには向かない。今まで、化学肥料を米作りに使用していたので、土壌改良に3年かかると言われました。
米の命が生きている。
酒は、生きている。

完全熟成堆肥といっても、鶏糞、酒粕、もみ殻、米糠、と様々な試行錯誤を行いました。その結果牛糞にたどり着き、土壌改良から3年目。その年の秋、1反あたり7俵の山田錦が収穫されました。完全熟成堆肥の有機肥料をやることで、地力がついた田圃では、安定した高品質の山田錦を自社栽培することに成功しました。山田錦の栽培の成功は、福井県では初めてのことでした。

万年雪を湛えた霊峰白山から流れる雪解け水は、長い年月をかけ、土壌のミネラルをたっぷりと吸収しながら自然に濾過された柔らかで清冽な伏流水です。敷地内の井戸から汲み上げて仕込み水として使っています。同じ水系の水で山田錦、五百万石を育てています。
永平寺町の風土で育った杜氏に蔵人たち。地元永平寺町民だからこそ、その地形、土壌、水、気候を知りつくしています。自然の力を借りて醸す日本酒は、造り手の技術がダイレクトに反映されます。
根気強くまじめであるというこの風土から生まれた人柄と、「美味しい!」と、喜んでいただきたいという醸造家としての情熱から生まれる頑な手間暇のかけ方こそが、こだわりの味わい「濃醇できれいな酒・明日への力水」となります。

商品名:the kurajo. No2_吉田酒造_純米酒/内容量:720ml/米(国産)、米こうじ(国産)/使用米:福井県産山田錦100%使用/精米歩合:85%/
日本酒度:+3.0/酸度:1.6/アミノ酸度:1.0/アルコール度:16.5度/製造元:吉田酒造株式会社
日本酒度:+3.0/酸度:1.6/アミノ酸度:1.0/アルコール度:16.5度/製造元:吉田酒造株式会社
the kurajo. / No2 吉田酒造 純米酒(720ml)
2,392 円(税込)
SOLD OUT
シリーズ一覧
 |
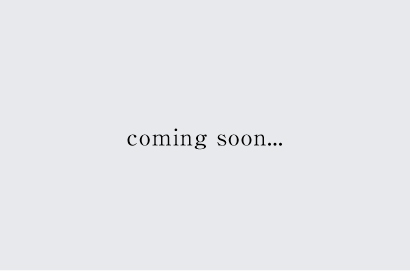 |
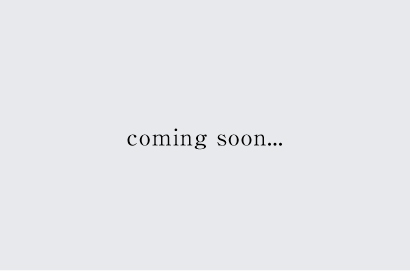 |
| ||||||||||||
